シロアリの被害について
伝統構法特に石場建の場合は足元などシロアリの被害が気になります。
まずはそのためにシロアリの生態と被害を受ける木材知る必要があります。
ネットで検索しても色々と出てくると思いますが、私は日本しろあり対策協会の「シロアリ及び腐朽防除施工の基礎知識」を参考に以下に概要をまとめました、参考にしてください。
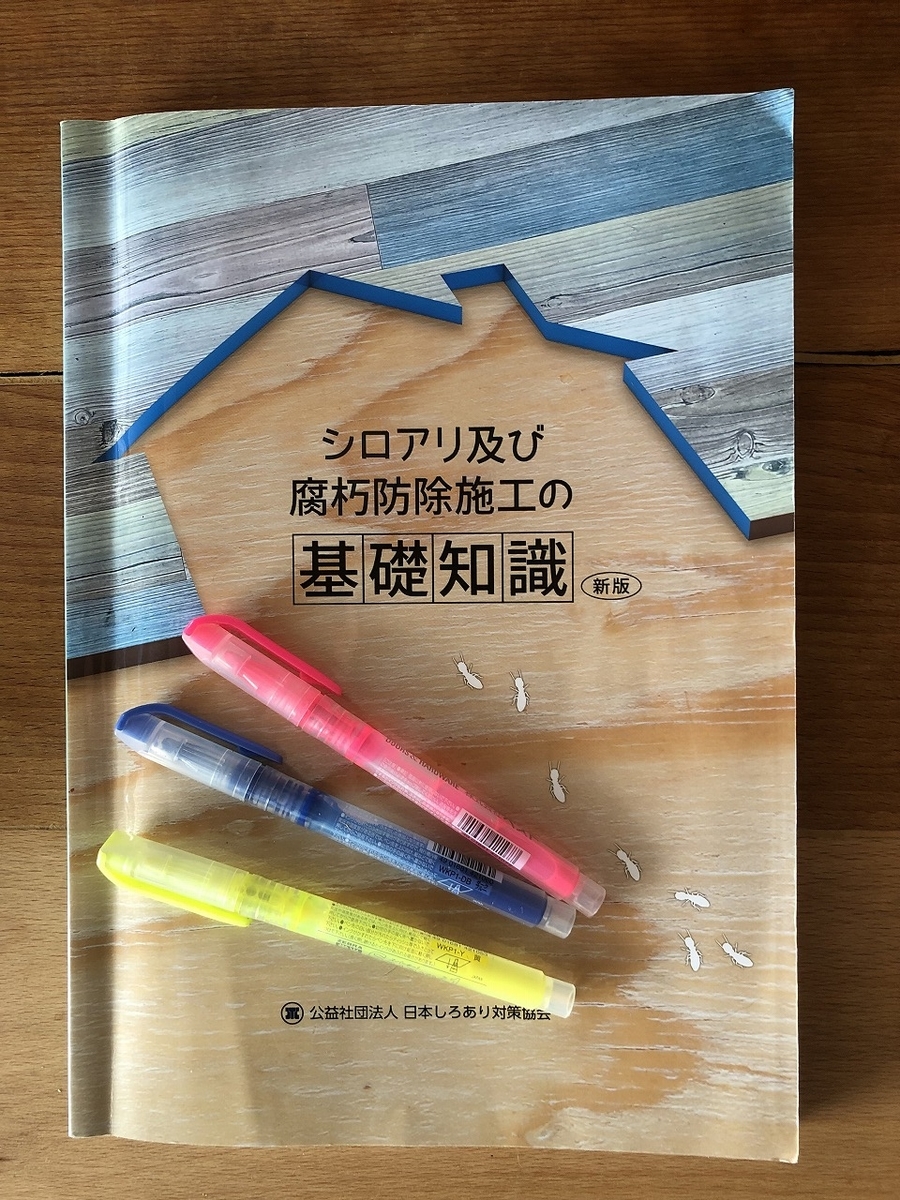
- シロアリの生態について
シロアリは蟻の仲間ではなく、ゴキブリに近い原始的昆虫でゴキブリ目シロアリ下目に属しています。3000種ほどが確認されていて、そのうち建造物に被害を及ぼすものは371種、残りの大部分は、枯れた木や落ち葉を食べ地球の物質循環に大きな役割を果たしている有益な昆虫です。
日本のシロアリは24種ほどで、建造物に被害を及ぼすものは、ヤマトシロアリ、イエシロアリ、アメリカカンザイシロアリ(カンザイ=乾材のことです)の3種が主なものになります。
①生息地域
・ヤマトシロアリ
寒さに強く広く日本全土に生息しており、埼玉県での被害のほとんどがヤマトシロアリです。※以下はヤマトシロアリを中心にまとめました
・イエシロアリ
世界のシロアリの中で最も加害の激しい種類。
生息地は、千葉県以西の本州南岸、四国・九州の低地などで被害の北限の記録としては茨城県潮来です。関東の内陸での被害はありません。
・アメリカカンザイシロアリ
アメリカやメキシコの太平洋沿岸地域が原産、日本へは家具などとともに持ち込まれ、屋内の乾材へ広がり家を建て直すほどの被害を与えています。
②注目すべき生態
・群飛
シロアリは巣から、種によって決まった時期・時間帯に多数の羽のあるシロアリが飛び出します、これを群飛と呼び、飛び出した雌雄が対となり新しいコロニーを作ります。
ヤマトシロアリでは、西日本4月下旬から5月、東北から北海道では6月に群飛します。
シロアリを発見する機会が最も多いのが、この群飛です。
・巣と蟻道
ヤマトシロアリは排出物や土壌等で蟻道を作り、加害場所が巣を兼ねています。蟻道を作りその中を通って地中や材面を移動、加害場所を広げていきます。イエシロアリと比べ、含水率の高い、部分的に腐朽した材に巣を作りますが、断熱材のような含水率が低い材料でも食害します。
・木材の加害習性
柔らかい密度の低い木材を好み、同じ木材でも細胞壁が薄く密度の低い早材が食害されやすい。また、心材(年輪の中心部分)はフェノール化合物などが蓄積しており、耐蟻性のあるものもありますが、辺材(年輪の外周部)にはそのような成分は少なく、ヒバやヒノキであっても辺材は簡単に食害を受けます。
コンクリート建築物にも侵入しますが、コンクリートそのものに穴を開けるのではなくひび割れ等の隙間から侵入します。そのほか、ウッドプラスチックや断熱材への食害も見つかっています。
・ヤマトシロアリの生態の重要点
ヤマトシロアリは特別に加工した固定巣は造りません。乾燥に弱く1日水を与えないと正常な活動を行うことができません。生存には液状の水が必要不可欠で生息環境は常に高い湿度に保たれています。相対湿度70~80%で摂食活動が活発になります。活動範囲を広げる場合は蟻道という乾燥や日射から身を守る通路を作り移動します。
そのため、湿った木材での被害が多く、その食害部位は湿っているか、近くに水場となる湿った場所がある必要があります。
住宅の被害場所としては、お風呂場・洗面所・台所などの水回りや最近では玄関部分からの被害が多くなっています。
個体の分化能力が非常に高く、少数からでもコロニーが再生されるといわれています。
昆虫の多くは、生息に不適な環境になると休眠することで生命を維持します、例えば冬の低温期は冬眠しますが、シロアリは休眠ができません。温度変化に弱い生き物と言えます。
気温6度内外で活動を始め、12度を上回ると活発になり、摂食活動は25~30度で最も高くなりますが、30度を超えると生存率が低下し、木材を消化するために共生している腸の中の原生生物も35度程度で死滅します。
そのため、夏の高温時には涼しい土中などへ、冬の低温時にも温度変化の少ない地下へ移動します。そのため、再侵入の防止が必要になります。
地下にトンネルを掘り、採食範囲の移動拡大を行っていますがヤマトシロアリは粘土の多い土壌に生息する傾向があります。
以上、シロアリ特に関東で問題となることの多いヤマトシロアリの生態についてまとめてみました。参考にしてください。
次回は木材について書こうと思います。